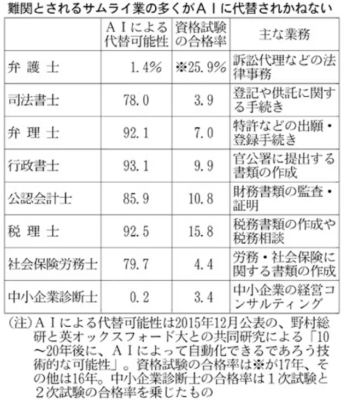こんにちは。迅技術経営の小川です。
前回に引き続き、2025年に新たに診断士としての活動を始めた大久保との対談動画をアップいたしました。
「資格取得までのリアル」と題して、前後編の後編ということで、「中堅診断士の成長過程」というサブテーマで、気づけば中小企業診断士として10年以上活動して中堅になってしまった私(小川)を中心に、未経験の状態で資格を取得してからどのようなプロセスで活動してきたのか、ということをお話しています。
お時間がありましたら、ぜひご覧ください。
「こんなことに答えてほしい、こういうテーマで話してほしい」ということがありましたら、ぜひコメントでご記載ください。
学生の方、すでに社会で活躍されている方、様々なハードルを抱える方、どのような属性の方であっても、「地域や地方、そこで活動されている方々のために、自身や資格の力を活用したい」という方と一緒に働くことができればと思っております。
石川県という地方の、しかも10人にも満たない会社に対してアクションを起こすことは勇気がいると思いますが、「小さな一歩」を踏み出してみませんか?
オンラインでも対面でも、弊社の士業と話すこともできますので、ぜひお問い合わせはこちらから、お待ちしております。
興味を持っていただいた方は、迅技術経営の採用ページもご覧ください。